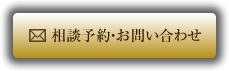T・Oさん 国際基督教大学 教養学部
<分析>
高校2年生の夏頃に当学院の門を叩き、入会しました。入会当初は、海外の大学へ進学するのか、日本の大学へ進学するのか決めかねている状況でした。よって、どのような進路を希望したとしても、対応できるように準備をしていくこととしました。
帰国生ということもあり、日本語力に不安があるとのことでしたが、それ以上に帰国生特有の「オーバーに述べる」という傾向が見られました。ただ、地域にもよりますが、海外ではそのような表現をある程度評価する側面もあることから、バランスを見ながら指導していく必要がありました。
帰国生ということもあり、日本語力に不安があるとのことでしたが、それ以上に帰国生特有の「オーバーに述べる」という傾向が見られました。ただ、地域にもよりますが、海外ではそのような表現をある程度評価する側面もあることから、バランスを見ながら指導していく必要がありました。
<施策>
日本語の基礎的な学びを行いながら、自身の主張に根拠を持たせる訓練を実施しました。本院が意見を述べたら、なぜそうだと言えるのか、どういった根拠でそれを述べているのかという問いを与え続けることとしました。
問いを立てる一方、本人らしさというものも大切にしていきました。本人が書くノートは日本語と英語が混ざり合った、本人にしかわからないものでしたが、これをあえて「きれいにしない」という手法で、本人の中で整理ができていれば良いということを徹底しました。
問いを立てる一方、本人らしさというものも大切にしていきました。本人が書くノートは日本語と英語が混ざり合った、本人にしかわからないものでしたが、これをあえて「きれいにしない」という手法で、本人の中で整理ができていれば良いということを徹底しました。
<効果>
高校3年生になり、次第に論理的に、根拠を持って話を展開できるようになっていきました。ある日、本人より「(SILS早稲田大学国際教養学部)とFLA(上智大学国際教養学部)とICU(国際基督教大学)、どこが(進学するのに)良いと思いますか?」と相談を受けました。どの大学も素晴らしいが、帰国生としての本人の性質を教員も学生も、システム面でも理解・支援してくれるのはICUだと思う、という旨を伝えたところ、本人の中で腑に落ちたようでした。結果、ICUより合格をいただき、最善の道が開かれたのだと思います。