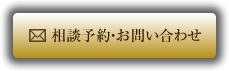Hさん 琉球大学 国際地域創造学部
<分析>
地方から上京してきた社会人でしたが、学習相談の時点で、その言動から明らかに勉強をしてこなかったということが見て取れました。
また、志望理由や将来像も曖昧であったことから、当初は入会をお断りする予定でした。
ところがこの生徒は、面談中に遠回しに断るようにフレーズに気づかず、入会する気が全面に出ており、今年度の受験はあきらめ、来年度受けることを提案したところ、そのようにするので入会させてほしいと、受け入れざるを得なかった、という状況です。
※実際には搭乗券を購入していた事情から受験はさせてほしいとのことであったため、「試験会場に慣れる」意味合いで受験し、下記のような事態が発生しました。
<施策>
勝負は翌年度にするとしても、やはり試験会場に行くのであるから、大学側に失礼にならないように、志望理由書等を整える必要がありました。
そこで、なぜ自分が再度仕事を辞めてまで学びなおす必要があると考えたのか、自身の背景や脳の中でどのような解釈をしたのかを客観視する練習を実施しました。
またこの生徒自身も職場で周囲の人が話し合っている様子を観察し、授業で学んだ人間の思考パターンを当てはめて分析をしていたようです。
さらに、台風による休講日も、講師に張り付き、余談であってもその発言をメモし、少しでも何かを学び取ろうとする姿勢がありました。
<効果>
「試験会場に慣れるため」の入試で合格を決めたことに、講師も生徒の家族も耳を疑いました。
後から面接内容などをヒヤリングしたところ、「首都圏には情報が溢れているが、何が正しいかを選択するための教育がない。都心に人も仕事もお金も流れている。勉学に勤しむことをしなかった地方出身の自分であるからこそ、正しい選択肢を地方の子どもたちに提供するために学ぶ必要がある。」といった趣旨の回答をアドリブで行うことができました。
小論文(面接含む)の力は、段階的についていくというより、地道な努力の末、突然覚醒することがしばしあります。この生徒もその一人ですが、試験直前にその現象があったと言えます。