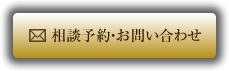Dさん 上智大学 文学部
<分析>
当学院主任講師がかつて勤務していた高校の生徒であり、日ごろから国際的・多角的な指導を受けている一方で、小論文の内容面での指導を受けたいとのことで、当学院へ入会されました。本人も話していたように、小論文の形式面は知っていても、どのような内容が評価されるのか、「形」に込められた意味などを理解していませんでした。本人が志望している学部(学術分野)についての知識があったため、そこを足掛かりに学習を進めました。
<施策>
今回の施策のポイントとしては、①日ごろから国際的な指導を受けており、討論などには慣れている、②しかし小論文における内容面での良し悪しの認識が、本人の中で十分ではない、③やりたいことがはっきりしており、それについての知識を自ら積極的に積んでいる、という点です。これらの条件を考慮し、あえて小論文の構成などの学びをせず、いきなり実践(本文作成)を実施し、まずは自由に書かせることにしました。そのうえで「なぜこういった点が指摘されるのか」という添削側の目線から指導を実施しました。これにより、一つひとつの言葉に深みを与えることが可能になります。さらに、将来像についてほぼ毎回講師とディスカッションを実施しました。
<効果>
当日の小論文では、学部テーマに対して政治的な視点や志望学部・学術分野、自分の使命感などとリンクさせ、多角的に論じる内容を回答していました。面接時には、自らの将来像を含め、この小論文の内容についても質問やコメントが面接官から挙がったようです。この多角的な視点(応用力)を持ちながらも、何を学び、将来どうなりたいのか、という軸と、それにふさわしい知識をもっていたというバランスが評価されたのであろうと推測されます。