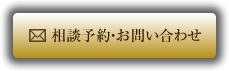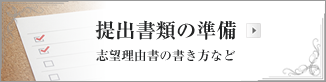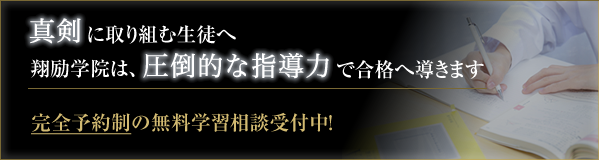字数は少ない方が難しい
小論文を実際に書き始める時に、「こんなに(字数が)たくさんの文は書けない」「指定された字数に達しない」といった声をよく聞きます。
字数が多いと大変だ、というのは、本当でしょうか?
いいえ、実は字数が短い方が難易度が高いのです。どちらかと言えば、文字数が多い方が書きやすいのです。大学入試における小論文は800~1200字程度で書くことが主流ですが、最近では600字以内で書くことを求める試験も増えてきています。
小論文の学習をはじめて間もない受講生は「字数が多い方が難しい」と言いますが、学習を進めるうちに字数が少ない方が難しいと言う傾向にあります。その理由について、「受験生」と「添削者」の視点からご紹介します。
受験生の視点
小論文の学習を開始したばかりの頃は、まず「文章を書く」ことそのものに抵抗や苦手意識があることが多いため、「文章を書く」ということがハードルとなります。学習を進めるうちに、そのハードルはクリアされていくのですが、次のハードルと出会います。
それは、「短くまとめる」「意見を一言で言い表す」ということです。短くまとめるためには、重複表現を避け、回答の中で展開してきた論点を、包括的にまとめる表現力・思考力が問われます。
この点から、受験生としては短く書くように求められる問題は、字数が多い問題よりも難しく感じやすいのです。
添削者の視点
添削者は、長い文章を、採点期間と短い時間・限られた人数で、それも多くの受験生のものを読まなければならない、というのは大変な作業です。
そのため、一人ひとりの添削・採点にそれほど多く時間をかけて読むことができません。できる限り効率的に作業を行うための一つの方法として、最初または最後の数行だけ読み、振り分けられる、ということもあります。字数の少ない小論文であれば、「読み飛ばす」部分が減り、回答の隅々まで読むことができます。細かいミスや、よく読むと矛盾している内容などを見つけやすく、より厳密な採点ができるのです。受験生側にとっては、チェックが厳しくなっているのです。
これらは、スピーチにたとえると、わかりやすいと思います。スピーチがうまい方は、話が短く、深い話ができます。スピーチがあまり上手でない方の場合は、同じ話を繰り返したり、話が脱線してまとまりがつかなくなり、長くなる傾向にあります。聞いている側も、長いスピーチよりも、短いスピーチを好む方が多いはずです。
翔励学院には、まったく文章を書けない生徒から、文章を書くことは苦ではないがダラダラと長く書いてしまう生徒など、入会時の状況はさまざまです。それでも当学院の指導を受けることで、端的でわかりやすい文章を書けるようになります。実際に指導を受けてみたいという方は、無料学習相談へお越しください。