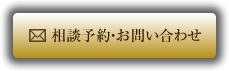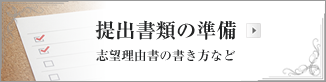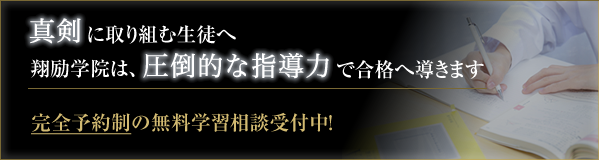必見!問題の出題傾向と対策
小論文の問題傾向は3パターン
実は、小論文の出題傾向は、他の教科と比べると非常に限定されており、的を絞りやすいです。
例えば、英語では発音やアクセントの問題、英作文、穴埋め、長文読解、文法に関する助動詞、時制、関係詞、不定詞、仮定法など、多種多様な出題が考えられます。
しかし、小論文の出題傾向は、大きく分けるとたった三つしかありません。
どのような問題が出るのか、また、対策していない分野が出題された場合にどうしようといった心配は、他の教科と比べると非常に少なくなります。
各大学や学部について過去数年分の問題を分析すると、その大学・学部ごとの傾向が見えてきます。例えば、「医療・看護系」の学部であれば、生命倫理、歴史的反省、評論、時事問題などがテーマとして挙げられます。 具体的な出題傾向については、その大学・学部の特徴や求める学生像を分析することで、十分に予測することが可能です。
小論文の問題は、大きく分けて以下の三つに分類されます。この三つの分類と各大学ごとの傾向を組み合わせることで、対策が自ずと可能になります。 ※その年によって出題傾向が変化することがありますが、過去数年の出題傾向や大学の現状から推測することができます。
1:主題型問題
ある一つのテーマについて、自身の賛否や自分の考えを述べる問題です。小論文の中でも最もポピュラーなタイプの問題と言えるでしょう。
このタイプの小論文では、結論そのものよりも、どのように展開し、なぜその結論に至ったのかという過程や論理が重要です。自分の考えをしっかりと示すためには、その背景や理由を論理的に説明することが求められます。
また、漠然としたテーマが出題されることも多いため、自ら問題提起を行い、その問題を解決するための筋道を立てていくことが高評価につながります。このようなアプローチは、受験生としての論理的思考力や問題解決能力を示す絶好の機会となります。
2:読解型問題
一つ、または複数の文章や記事を読み、その内容について、あるいはその内容を前提として回答する問題です。このタイプの問題は近年増加しており、大学によっては英語で出題されることもあります。
このような問題では、「正確に内容を読み取る」ことが非常に重要です。文章の中で著者が何を伝えたいのかを理解することはもちろん、複数の文章が出てきた場合には、それらがなぜ出されているのか、つまり「問題の意図」を探ることが求められます。
主題型の問題とは異なり、自分の述べたい内容に無理に議論を引き寄せると、「的外れ」の回答になってしまいます。自分の意見と相手の意図をしっかりと見極め、文章との対話を丁寧に進めていくことが、合格へのポイントとなります。
3:資料型問題
アンケート結果や市場調査など、グラフや数値といった資料を参照して回答する問題です。これらの資料が他の文章と一緒に出される場合もあります。こうした問題では、数値という視点から「何がわかるのか」「何が問題であるのか」「どのように解釈すべきか」といった洞察力が求められます。
特に、志望する分野に関連する内容から出題されることが多いため、数値から適切な解釈を導き出すには、志望分野の入門書程度を読んで情報収集をしておくことが望ましいでしょう。
翔励学院の小論文指導では、上記のパターンをさらに細分化し、各大学や学部の傾向を研究した上で、どのパターンを優先的に習得するべきかを判断します。もちろん、出題傾向が突然変更されることもあるため、あらゆるパターンに対応できるよう学習しますが、その中でも優先順位をしっかり定めて進めることが重要です。
小論文学習の進め方について相談したい方は、ぜひ当学院の無料学習相談にお越しください。