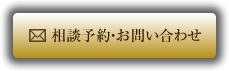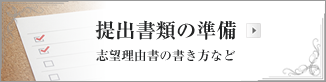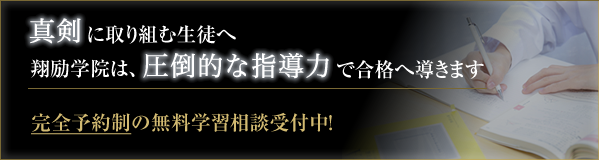小論文の公式
小論文の公式は、3つのことを押さえる
小論文を書く際、まず重要なのは「問題提起」です。これは、出題テーマに関連する問題を自分の言葉で簡潔に述べる部分です。この段階では、何が問題なのかを明確にすることが大切です。
次に「自分の意見」です。問題提起の後、自分がどのように考え、どのように解決すべきかを述べます。自分の意見は、具体的な事例やデータを使って裏付けをすることで説得力が増します。この部分が最も重要であり、あなたの考えがきちんと伝わるように工夫しましょう。
最後に「結論」です。自分の意見を述べた後、その考えがなぜ重要で、どのように社会に貢献するのかを簡潔にまとめます。結論では、問題解決の方向性を示し、問題提起と自分の意見をしっかりと結びつけることが求められます。
この「問題提起」「自分の意見」「結論」の3つの要素を順番に書いていくことで、小論文の骨組みができます。これに自分の考えや視点を加えることで、論理的で説得力のある小論文に仕上がります。
翔励学院では、この「小論文の公式」を基に、効率的な学習をサポートしています。小論文に悩んでいる方、書き方に迷っている方は、ぜひ無料学習相談にお越しください。
1:序論 100~150字程度
小論文の導入部分にあたります。
単なる導入ではなく、問題提起、この小論文で述べる内容、またその動機などを、短い文章で述べる必要があります。
単なる導入ではなく、問題提起、この小論文で述べる内容、またその動機などを、短い文章で述べる必要があります。
2:本論 500~600字程度
小論文の中軸になる部分です。
ここでは自分の主張、その理由や根拠、事例などを書きます。
自分の好き嫌いで書くのではなく、論理的に、客観的に書き進めることが重要です。
本論では、自分の主張だけを書くだけではなく、多角的な視点を書くことも求められます。
そのため、反対意見、並びに反対意見の論拠なども、自分の意見と同様に、公平に議論することが求められます。
ここでは自分の主張、その理由や根拠、事例などを書きます。
自分の好き嫌いで書くのではなく、論理的に、客観的に書き進めることが重要です。
本論では、自分の主張だけを書くだけではなく、多角的な視点を書くことも求められます。
そのため、反対意見、並びに反対意見の論拠なども、自分の意見と同様に、公平に議論することが求められます。
3:結論 100~150字程度
文字通り、小論文全体の結論です。本論で述べたことの重複とならないように結論を述べ、文章全体を締めくくます。
この公式に意見を入れることで、それまでバラバラであった考えや発想をまとめることができます。この公式は小論文の参考書や他の情報サイトなどでもよく言われるものです。
では、序論・本論・結論に何を入れるべきかは、志望する学部・学科によって異なります。翔励学院では生徒の志望先・分野ごと、さらに生徒の個性に応じて書き入れる内容をアレンジし、指導しています。序論・本論・結論そのものは知っているけれど、では自分の場合は何を書き入れれば良いのかとお考えの方は、無料学習相談にお越しください。当学院講師がお話を岡外し、指導させていただきます。
この公式に意見を入れることで、それまでバラバラであった考えや発想をまとめることができます。この公式は小論文の参考書や他の情報サイトなどでもよく言われるものです。
では、序論・本論・結論に何を入れるべきかは、志望する学部・学科によって異なります。翔励学院では生徒の志望先・分野ごと、さらに生徒の個性に応じて書き入れる内容をアレンジし、指導しています。序論・本論・結論そのものは知っているけれど、では自分の場合は何を書き入れれば良いのかとお考えの方は、無料学習相談にお越しください。当学院講師がお話を岡外し、指導させていただきます。