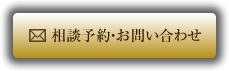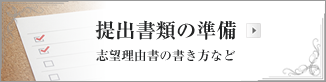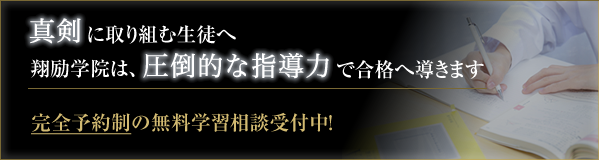小論文と作文はまったく違う
よくある誤解
小論文の学習を始める際によくある誤解について紹介します。
この誤解を抱えたまま学習を進めてしまうと、どんなに素晴らしい内容の小論文を書いても、残念ながら評価されないということが起こり得ます。
いわば、短距離走で一生懸命走っているのに、コースを外れてしまっている状態です。どんなに速く走っても、失格になってしまうのです。
では、どのような「誤解」があるのでしょうか。それは、「小論文と作文」を混同し、両者の違いがわからないということです。この二つは似ているように思えるかもしれませんが、その性質は全く異なります。
作文
作文は、テーマや内容について制限が少なく、自由に書くことができます。また、「主観」や「感想」を含んでも問題ありません。例えば、「読書感想文」はその代表的な例です。ご存じの通り、「感想文」とは、本人が「何をどのように感じたか」を書くものであり、主観的な内容であっても全く問題ありません。作文は、ブログやSNSで書くような、日常的に感じたことを自由に表現するようなものでも構いません。
一方、小論文には明確なルールがあります。このルールを守らないと、最悪の場合、採点されないことがあります。そのため、小論文のルールをしっかりと理解し、守ることが非常に重要です。
小論文のルール
小論文にはさまざまなルールがありますが、その中でも代表的なものが「客観性」です。小論文では、主観をできるだけ排除し、客観的に書くことが求められます。音楽や美術といった芸術作品のように、受け取り方が人によって異なるものとは違い、小論文は、異なる背景を持つ人々が「同じ尺度」で読めるものでなければなりません。
例えば、「遠い地域」と述べた場合、作文では問題ない表現ですが、小論文では避けるべきです。「遠い」という言葉の定義は人によって異なります。1キロメートルで遠いと感じる人もいれば、100キロメートル以上で遠いと感じる人もいます。このように、「遠い」という表現は人によって異なるため、読み手が同じ認識を持つことができません。これが主観的な表現です。これを客観的にするためには、たとえば「約100キロメートル先の地域」や「東京から大阪へ行くよりもさらに遠い地域」など、具体的な数字や比較を用いて、読み手が同じ認識を持てるようにします。
小論文の学習は、このようなルールを理解することから始まります。その他の小論文のルールについて知りたい方は、当学院の無料学習相談にお越しください。当学院の講師が、小論文を書く際に欠かせないルールをお伝えします。