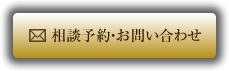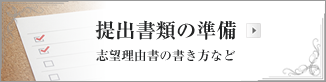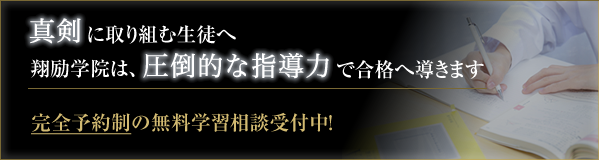小論文ではどのようなテーマが出題されるか
小論文のテーマはどのようなものが出題されるか、これは受験生にとってはもっとも気になるところだと思います。小論文の出題形式は、あるテーマを出し、それについて回答するものもあれば、課題文や資料などを読ませて、それについて論じさせるものもあります。
後者の場合、はっきりと「テーマ」について書かれていない場合もありますが、課題文の背後にあるテーマを読み取り、回答する必要があります。
後者の場合、はっきりと「テーマ」について書かれていない場合もありますが、課題文の背後にあるテーマを読み取り、回答する必要があります。
小論文のテーマは誰が決めるか
小論文の問題は、大学ごとに違いはありますが、原則その学部・学科の入試担当教員が作成していると考えられます。大学の教員の場合は、博士号を取得している、専門の研究分野をもたれている方々です。ご自身の研究分野、その分野の現状等を考慮し、問題が出題されます。
専門分野は出題されるか
大学へ入る前の受験生に対し、専門的な内容を出題するのかどうか、という点に関して、答えは「イエス」です。その分野をこれから学ぼうとしているのであれば、高校生であっても何かしらの形で触れ、自発的に学んでいるというのが、求められる姿勢です。
たとえば、音大に入学したいという人がいて、楽器もまったく弾けない、ボイストレーニングなどもしていない、音楽史についてまったく知らずに受験するということは、まず考えられないでしょう。
同様に、小論文を使って受験をするというのは、これから学びたい分野について、どの程度学んできたかが問われるような問題が出題されると考えて良いでしょう。
たとえば、音大に入学したいという人がいて、楽器もまったく弾けない、ボイストレーニングなどもしていない、音楽史についてまったく知らずに受験するということは、まず考えられないでしょう。
同様に、小論文を使って受験をするというのは、これから学びたい分野について、どの程度学んできたかが問われるような問題が出題されると考えて良いでしょう。
専門分野を連想させる問題
直接的に専門分野について問われる問題が出題されなくても、専門分野を連想させるような問題が出題されます。
たとえば、教育学部を志望しており、問題の中に「デジタル化」というキーワードが出てきたとします。この場合は、「教育」「デジタル化」という言葉から「ICT教育の利点と問題点」などについて触れておくと良いでしょう。
また、医学部などの将来この職業に就く前提の学部の場合には「医師の役割」など、その職業についてどの程度理解しているか、ということも問われます。
翔励学院の小論文指導は、こういった専門知識の学習についても、しっかりとサポートをしています。医療・法学・芸術など、入試の時点で専門性の高い問題が出題される分野もありますが、あらゆる分野での対応が可能です。実際に指導を受けてみたいとお考えの方は、無料学習相談へお越しください。