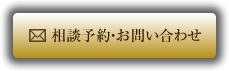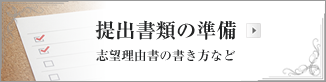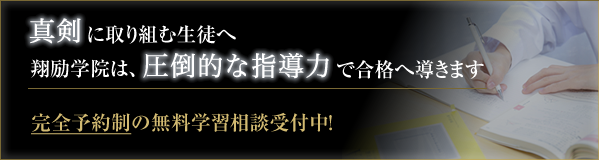添削指導を受けた後が重要
小論文の学習において、添削を受けるということは、もっともスタンダードな方法です。
現在では当塾のような学習塾の形態のみならず、通信教育、模試など、さまざまな方法で添削を受けることができます。添削を受けることで、小論文の質が向上する学生と、何度添削を受けてもなかなか上達しない学生がいます。
当学院は、闇雲に添削だけを行うことには消極的です。添削を受けた後に、それをどのように活かすか、ということを十分に理解していないと、添削は意味がありません。
そこで、添削指導を受けた後、どうすれば小論文がレベルアップしていくのかを紹介します。
添削指摘の意図を考える
添削指導は、表面的な言語の訂正(表現)について修正する場合もありますが、思考力や教養を問うような指摘の方が、遥かに重要です。
添削指導をうまく活用できる学生は、ただ指摘された内容をすぐに書き直すのではなく、なぜ指摘されてしまったのかを考えます。
たとえば、「具体的には?」といった指摘があったとします。このコメントの意味することは「具体性がない」ということですが、具体的に述べるためには、それなりの知識が必要です。具体性がない場合には、「書き方」の問題というよりは、具体的に述べられるようなネタ(知識)が不足していることが大半です。
そこで、添削者の意図、「具体的に述べられるほどの知識をもって臨んでいますか?臨んでいるのであればそれを書くべきですし、そうでないのであればまずは知識を身につけていく必要があるのではないですか?」という意図を読み取ることです。
他にも同じようなことで指摘されていないか
添削で指摘された内容に共通点はないか、過去に同じようなことをしてはいないだろうか、丁寧に確認することが必要です。
書き直す
添削指導を受けたら、再度書き直すことは必須です。たとえ提出の必要がなくとも、もう一度書き直す。この地道な作業を欠いて、小論文が上達することはありません。
一般的な科目に置き換えますと、添削指導を受けてそのままにしておくことは、数学で間違えた問題をそのままにしておくことに似ています。同じ間違えをしないように、繰り返し練習をする、これは小論文でも同じことです。
翔励学院では、無料学習相談において、小論文模試等で添削されたものを持参していただければ、今後どのように学習すれば良いか、ご案内しています。