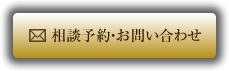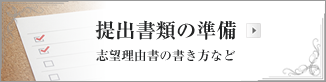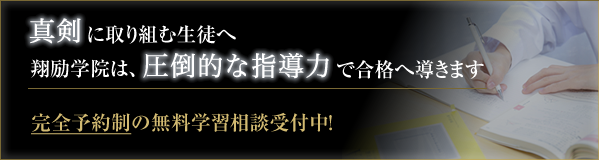高校2年生までの取り組みが勝負の分かれ目
落ちる小論文は内容が薄い
大学入試で落ちる小論文には、いくつかのパターンがあります。
代表的なものの一つとして「内容が薄い」状態があります。
かつて、小論文は形式的なものであるとも言われていましたが、現代の大学入試は、そのような「表面上」の小論文で合格できるほど甘くはありません。
内容が薄いというのは、具体的には、単なる自己主張となっている場合や、根拠が不明確な場合などが、それにあたります。
たとえば、<教育>について論じるとします。
教育というのは、かなり幅広い言葉になりますから、学校教育、家庭教育、社会教育、生涯教育など、何かに絞る必要があります。
まずこういった「論点を絞る」ことができているか否か、という点があります。
内容が薄い小論文は、論点が絞りきれていないということが多々あります。
では論点を「学校教育」に絞ったとします。
学校教育について論点を絞るのであれば、学校とは何か、法律上、学校はどのような位置にあるか、学校を取り巻く近年の話題は何かなど、学校教育についての基本的知識に基づいて論じられているかどうか、ということは重要です。
つまり内容が薄い小論文というのは、こういった知識に基づいておらず、「何となく」や「思い込み」で書いている、またはこういった知識に基づいていることが読み取れないものを言います。
内容のある小論文を書くためには?
内容のある小論文を書くためには、まずは知識を入れていくことが大切です。
それも、高校の問題集にあるような穴埋め式の単語を覚えるような方法ではなく、
たとえば歴史上の人物の概観や現代社会の範囲にある人権問題など、
自身が学びたい(志望する学部)に関連する内容について「説明できる」力を養うことです。
「説明するのが難しい」と言っている人の多くは、実際には説明するための表現力の前に、そもそも「知識が不足している」ということが原因です。
説明する内容がないのに、表現方法の小手先だけでどうにかしようとしても、限界があります。
しっかりとした知識に基づいて、論理的に説明できるようになることが、小論文での説得力を高めます。
高校2年生までに行うべきこと
この知識は、まず自分が志望する学部に関連する範囲で、高校生の教科書レベルの内容については、一通り把握しておくようにしましょう。
教科書範囲の内容について一通り学習している場合には、時事ネタの収集に入ります。
時事ネタは、試験の行われる数ヶ月前ですとか、直近のニュース等は扱いにくいため、試験を受ける一年程度前のものや、ある程度議論が出尽くしているものから取り組むようにしましょう。
高校3年生になってしまったら、もう知識を増やしていくばかりに時間を割くことはできません。過去問演習や添削・志望理由書の準備など、実践面でやるべきことが多岐にわたります。そのため、高校2年生の12月までには、上記の一通りのことを終えていることが理想的です。
高校3年生の緊急対応
高校3年生になって小論文の学習を始める場合、さらに知識面での不足がある場合は、緊急対応を余儀なくされることがほとんどです。
緊急対応をする場合、もちろん知識の習得も行いますが、たとえば10月の入試の場合、4月から準備を始めたとして、たった半年でそれほどの知識をカバーできるかと言えば、難しいと考えた方が良いでしょう。
それでも短期間で急進的に成長した学生たちも、実際にはいます。最後はやはり「志」がものを言います。
合格したいという強い気持ちのある受講生は、なりふり構わず行動し、勉強します。自分より下の学年たちに紛れていたとしても、勉強会に参加します。
早めに準備をすることはもちろん大切ですが、その基本となるのは、やはり「志」に他ならないのです。
翔励学院では、入会時期に応じて戦略を立てています。
当然のことですが、入会時期が早ければ、その分合格までスムーズに進みます。入試で小論文を使うという方は、お早目に無料学習相談へお越しください。