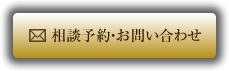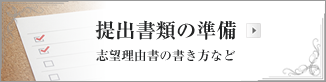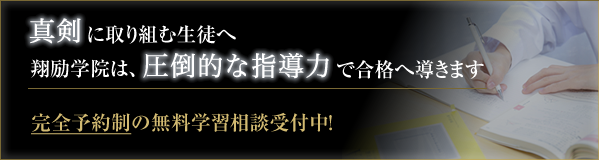小論文の下準備~後編~
構成メモの作成
別ページで紹介したブレインストーミングが完成したら、「構成メモ」を作成します。この構成メモが完成すれば、小論文はほぼ完成と言っても過言ではないほど重要です。
構成メモは、回答字数が800~1200字程度の場合、一般的には「序論」「本論Ⅰ」「本論Ⅱ」「結論」の4つの区分に分けることが多いと考えれば良いでしょう。
※問題の出題傾向によっては、上記の構成が変更されることもあります。
自分の論点を決める~本論Ⅱ・結論~
構成メモでまず決めるべき内容は、自分の論点です。小論文では、限られた文字数の中で、自分の主張とその根拠を述べなければなりません。これが最も重要な軸となるので、自分が一番伝えたいこと、そしてその理由・根拠を明確に決定します。この部分は、構成メモにおける本論Ⅱと結論にあたります。
構成メモの段階では、ダラダラと文章にして書くのではなく、箇条書きにします。「何を伝えたいのか」「なぜこの主張をするのか(根拠)」という点を、シンプルに書き出すことを目指しましょう。
多角的な意見を取り入れる~本論Ⅰ・序論~
小論文では、テーマや課題についての知識も問われます。そのため、本論Ⅰでは多角的な意見を述べたり、序論で言葉の定義を行うなど、本論Ⅱとは異なるアプローチが求められます。
ここで注意すべきことは、できる限り客観的に多様な意見を紹介する一方で、本論Ⅱで本論Ⅰの意見を乗り越えることです。つまり、さまざまな意見を述べた後に、なぜ本論Ⅱの意見を選ぶのか、明確な理由を示す必要があります。多様な意見が書かれているのに結局何を伝えたいのかわからないような小論文では意味がありません。そのため、本論Ⅱと結論から先に構成を整えることが重要です。
ボリュームを決める
上記のように小論文の内容について決めることと並行して、本文のボリュームを決定します。どの区分にどの程度の行数を使うのか、段落はどうするかなど、大雑把なもので構いませんが、これを怠ると字数の調整ができなくなるため、必ず行うようにしてください。
翔励学院では、小論文を書き出す前の準備指導を徹底しています。この準備をきちんと行うことで、小論文は見違えるほど良くなります。実際に指導を希望される方は、当学院の無料学習相談にお越しください。