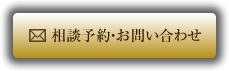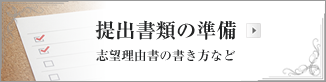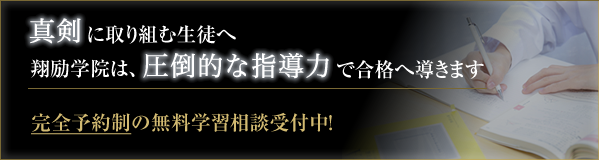小論文の下準備~前編~
小論文は「下準備」で決まる
小論文は、これから説明する「下準備」によって大きく左右されます。回答用紙(原稿用紙)に本文を書き出す前の下準備をしっかり行うことにより、小論文の内容・方向性・構成まで確定させることができます。60分の回答時間であれば、10~15分程度、この下準備に使うことをお勧めしています。
「60分のうち15分も?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には「15分しか」ないのです。それだけ、下準備でするべきことが多くあります。下準備で行うことは、大きく分けて2つあります。今回は、下準備の前半部分について説明します。
ブレインストーミングを使う
まず最初に行うことは、ブレインストーミングです。ブレインストーミングは、研修会などのグループワークでよく用いられる方法ですが、大学入試における小論文対策としては、これまではあまり実践されてこなかったように思われます。しかし、近年ではこの方法を指導するケースが増えてきています。その背景には、小論文を使用する受験者数の増加に伴う受験生のレベル向上や、出題傾向の多様化などが挙げられます。
このブレインストーミングは、とてもシンプルな方法で行うことができます。具体的には、問題そのものや課題文・課題資料に含まれている、あるいはそこから読み取れる「キーワード」を抽出し、そのキーワードに関連することや思いつくことをできる限り多く書き出す方法です。
たとえば「学校」というキーワードを選んだ場合、学校に対する自分や他者のイメージ、学校に関連するもの、学校の役割など、さまざまなキーワードを次々に書き出していきます。さらに「学校」という言葉から派生する次のキーワードに関連するアイデアも追加していきます。(例:学校→勉強→読書・・・)ここで重要なのは、考え込みすぎず、思いつくままにどんどん書いていくことです。まとまりや結論がなくても構わないので、アイデアをできる限り広げていくことがポイントです。
拡散したアイディアを整理する
続いて、上記のように拡散させたアイディアや散りばめたキーワードを整理します。共通するキーワードや関連性のあるキーワード同士を丸で囲んだり、さらに理由や根拠がしっかり述べられそうなキーワードにも同じように印をつけます。この作業を通じて、重要なキーワードや主張したい内容が浮き彫りになります。そして、特に伝えたいこと、一番強調したい点については、もっとも目立つように印をつけます。印のつけ方は、各自の方法で構いません。
ただし、印をつけたキーワードを必ずしもすべて本文で使用する必要はありません。また、ブレインストーミングで出た結論部分がそのまま小論文での結論になるわけではないこともあります。
このプロセスでは、自分の頭の中がどのように整理されているのか、直感的にどのように考えているのかを明確にすることが目的です。その直感が単なる思いつきなのか、それともしっかりとした理由や根拠に基づいているのかを検討する作業でもあります。
この方法は、右脳を使った作業です。後編で紹介する左脳を使った下準備方法と組み合わせることで、広がりとまとまりを兼ね備えた小論文を書くことができます。
翔励学院では、小論文を書き出す前の準備指導を徹底しています。この準備をしっかり行うことで、小論文は見違えるほど良くなります。実際に指導を希望される方は、当学院の無料学習相談へお越しください。