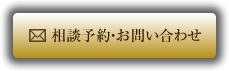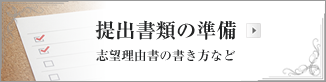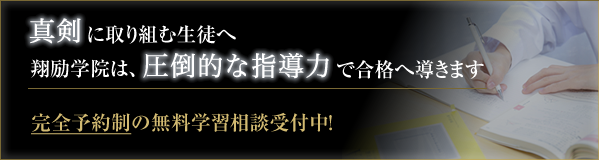「文章力」は、書くだけでは身につかない
文章力がない?
小論文を上達させるために、皆さんはどのような練習を行っているでしょうか。ひたすら文章を書くという手法がありますが、この方法では、なかなか上達しません。
「小論文」という言葉を聞いて、苦手意識を持っている学生が、「私ムリ、『文章力』ないから!」と言っているのを、よく耳にします。そもそも、ここで言う「文章力」の定義は、厳密に言えば文章表現力のことを指していますが、本来的な意味での「文章力」とは少し異なります。
ただ書くだけではダメ
文章力は確かに表現力の要素も含んでいますので、それ自体は誤りではありませんが、ただひたすら文章作成の練習、つまり文章を書くことに取り組む練習方法は、非常に効率が悪いのです。それに気づかずにひたすら書き続けるのは、非常にもったいない話です。
では、なぜひたすら書く練習をするという方法が取られるのでしょうか。それは、他の教科で演習(問題を解く)を行うことで、解法を理解し、身につけるという手法が使用されているからです。
たとえば数学では、公式の理屈を理解するのではなく、公式を「覚える」または「使えるようになる」ために「演習」を行います。この方法は、客観試験(答えが決められている問題)においては効果的です。たくさん練習することで、体に覚えさせていくという、よく行われる学習方法です。
小論文の学習においても演習は行います。演習を通じて、言葉の使い方を覚えることができます。どこでどのような言葉を使うべきか、理屈が理解できていなくても感覚的に理解しているので、表現力がつきます。しかし、このように演習を繰り返して表現力だけを訓練しても、十分とは言えません。
文章は「思考」から
文章というのは、その人の思考が反映されたものです。表現方法だけを修正しても、その人の発想や論理、思考力を訓練しなければ、根本的な改善にはつながりません。
よく例として挙げることですが、「食肉」という言葉を考えたとき、正反対の二通りの思想から異なる言い方ができます。それは、「殺害」という言い方と「食物連鎖」という言い方です。「殺害」という場合は食肉反対の立場を、「食物連鎖」という場合は食肉賛成、あるいは容認の立場を表していることがわかります。
このように、発せられる言葉はその人の思想や立場を反映するものです。書かれている言葉、表現そのものだけではなく、どのような思考があるのか、論理的であるか、客観性があるか、説得力があるかなど、その人の思考力が問われるのです。
文章力を身につける
文章力を身につけるためには、まず自分の頭の中を整理し、さまざまな意見や立場、思想を理解することから始めることが望ましいと言えます。これには思考力の訓練が必要です。
自分の頭の中を整理することは、なかなか一人では難しいものです。そこで、ワークシートを使ったり、本や他者との対話を通じて、自分の考えを整理する方法が有効です。
翔励学院が、単に決まりきった文言を教え込むのではなく、対話を重視し、考える力を養う指導を行っているのは、この理由からです。書き手の思考力を鍛えることで、どんな問題にも対応できる小論文を書くことができるようになります。実際に指導を受けてみたい方は、無料学習相談へお越しください。